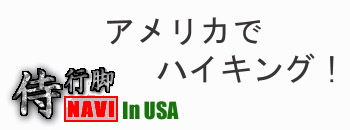Light weight hiker御用達というと数年前まではalcohol stoveという認識だった。アメリカではどこのcar parts shopにも置いてある車用の不冷剤(yellow Heet)を燃料として使えるため安価で入手性が非常によく、またストーブが自作できるというのもUL hikingの流れに合っていて大流行となった。しかしここ数年で状況はかなり変わってきた。まずHiking人口が大きく増加したことなどによりどこでも比較的容易にGas Canisterを入手しやすくなった。宿などのfront deskでGas Canisterを見かける機会も増えてきたように思える。また相次ぐwild fireの発生により火災発生率の高いwood stove, Alcohol stoveは禁止される傾向にある。そしてGas Canister stoveも非常に軽くなってきた。
Snow Peakの軽量なものは60gを切るほどである。とはいえstove自体の重量はAlcohol stoveの方がまだまだ軽いのだが、wind screenや燃料まで合わせたcooking systemとして考えると
gas canister stove systemの方が遥かに軽い。例えば一週間くらいのhikeを考え、1日1回夕食時のみのstove使用で進めるとすると、概算となるが
Alcohol Stove systemでは
アルミ缶ストーブ(15g)+ウインドスクリーン(30g)+燃料ボトル(30g)+アルコール燃料(350ml-280g) =355g
に対しgas Canister systemでは
ストーブ(75g)+ガス管(110g入 缶重量100g合わせ210g)=285g
と70gもGas Canister systemの方が軽い。1、2泊の短い期間だとその差は縮まるだろうが、UL hikerが気にする a.)軽量・コンパクトというところでは優位性はない。ただし未だAlcohol stoveはb.)入手性のよさ、c.)静音、d.)燃料が安い(山岳用品店にお金を貢いでいる人は高いと思ってるらしい・・・)という利点があるが、元々、e.)調理に時間がかかる、f.)火力調整(火の勢い・継続時間)が困難という欠点も併せ考えると軽量stoveのsolutionとしてCanister Stoveを選ぶhikerは今後も増えていく傾向にある。
Canister Stoveの欠点というとg.) 残量がわかりにくい h.)風防がつかいにくい i.)低温時の取扱に注意j.)stoveの重心が高く不安定の4点に加え、k.)空き缶の始末が必要なことだろう。ガス缶自体を熱してしまうと爆発の危険があるため風防(wind screen)を使った燃焼の効率化ができないが、Alcohol stoveから比べれば雨・風には強く点火も容易であり、風防自体の必要性は小さいし、そもそも重量比較でわかるように燃料・比重効率がAlcoholより遥かに良いのでので、この点はあまり問題とならない。ただし残量に関しては水にガス缶を浮かせてどこまで沈むかでだいたいのところを把握はできるものの、現地購入ではガス缶メーカーがいつもの慣れたものになるとは限らないし、やはり最後の方がわかりにくく、あと2回煮炊きできるのかそれとも1回しかできないのか把握するにはかなり経験が必要である。残量を知るためのチェッカーも売られているが重さ的に本末転倒になってしまう。Alcohol stoveの優れたsystemであるcaldera coneは風防がポットと一体化するため非常に安定しており、長年使用しているが未だに一回もポットを倒してお湯をこぼしたことはないというか構造的に倒すのは難しい。 これに比べガス缶・ストーブ・ポットと3段積みになったcanister stoveは重心が高く不注意にポットに触れたりすると熱湯がそこらじゅうに飛び散る可能性もある。Caldera cone systemなどから移行する方は特に注意が必要だ。幸いにして調理時間は強い火力のおかけで短くなるので注意を払わなければいけない時間は短くなる。
日本語ではLPGのことをプロパンガスというので非常に混同しやすいのだが、Gas Canisterに使われているのはこのLPGでこれはpropane(C3H8) , butane(C4H10)という2種類の混合ガスである。propaneには異性体にはないがbutaneにはiso-butaneという異性体があるため、実際には3つの異なる沸点をもつ混合ガスで、それそせれの沸点は1気圧の元でbutaneが摂氏-0.5度、
iso-butaneが摂氏-12度、propaneが摂氏-42度となっている。標高が高くなると沸点が下がるので高地では少し低い温度まで大丈夫(1000m高くなると沸点は約3C下がる)だが、寒い場所ではbutaneが気化しなくなってガスが残っているのに出てこずに火がつかない・消えてしまう気化不良が発生しやすくなる。とはいえ沸点が低いということは爆発しやすいということでもあり、butaneの方がpropaneに比べて安全だし、ガス缶の剛性も少なくて良い=ガス缶が軽いので値段は別としても闇雲に純粋なpropane燃料がよいというわけでもない。(沸点が高いものの方が液化させ易く加工が容易なのでbutane主体のものが安価である。)また沸点よりまわりの気温がすこしでも高ければよいかというとそうでもない。というのは液化ガスが気化するときに熱を必要とするため(気化熱)、使用に際し缶は自らを冷やしていく。このため沸点と周りの温度にある程度マージンがないと次第に缶が冷えてやはり気化不良となる。キャンプ向けとされているものでも火力が大きく低温で使うことが少なそうなBBQ用品向けなどはbutaneが主体の製品で、逆に寒冷地向けとなっているようなものはiso-butaneとpropaneのみで構成されていたりする(また缶の内部に媒体をいれて気化を促進させるような工夫がされているものもある)。このへんの特性を理解しておけばあらかじめ氷点近くまでさがりそうな寒冷地に行く場合には寒冷地向けのものを購入したり、点火する前に缶を体温で温めたりと対応することもできるし、逆にそんなに寒くないhikeであれば安価で軽量なbutane缶で十分だという判断ができる。気化熱については、かなり寒い時期に不用意に使用中に温かいと思ってガス缶に触ると気化熱によりひどく冷えているため指先が缶に張り付いたりすることもあるので注意しよう(ガムテープなどを予めはって予防するのもよい)。空になったガス缶はゴミとして持ち帰るのはもちろんだが、何も出てこなくなるまで完全に空にした上で缶切りなどで穴をあけてから所定の場所に捨てよう(購入できる場所ではたいてい捨て方もわかる)。