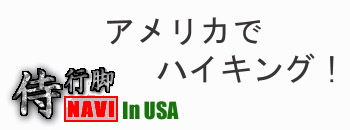long distance trailを歩く、またはJMTやWTの様なpermit取得を半年前に考えなければいけないという時、ひとつ気になるのが積雪の状況である。例えば2011年seasonは太平洋岸沿いでは大変な大雪seasonで平年にくらべて一ヶ月以上積雪が溶け切るのが遅く、Sierra NevadaやCascadeなどでは8月末でも雪がたっぷりと残ったtrailがあちこちにあった。この年は2月頃までは積雪は平年並みだったのに通常雪が溶け始める3月どころか4月になっても雪は積もり続け5月末に夏を迎えたときの残雪量は20年来にない数字だった。こんな年は例外としても通常は3月中に積雪のpeakを迎え以後減っていくもので、3月に入れば今年の積雪量はだいたいわかり平年との比較もすることができ、ある程度の予測が出来るようになる。アメリカ西部でこの予測に使えるのがSNOTEL(Snow telemetry – 積雪遠隔測定システム)というアメリカ農務省配下のNRCS(Natural Resources Conservation Service – 自然資源管理局)によって設置されたシステムであり、積雪量・気温などをはじめAlaskaを含む西部諸州(WA, OR, CA, NV, UT等)の500箇所以上から毎時自動でデータを採取しデータベース化してくれており、Internetにより容易にデータにアクセスできるようになっている。システムの設置場所が山岳部のアクセスのなかなか難しい場所にあることもありhike用の予測を立てるには非常にあてになる。元々農家向けの情報のため、積雪量が雪の深さでなくどれだけの水資源として残っているのか(snow water equivalent – inch)という表記になるが例年との比較であれば特に大きな問題ではない。.CSV形式でこれまで蓄積したデータを引っ張り出すこともできるので自分でグラフなどを作成して調べることもできるが、平年との比較程度ならばreport generatorから場所とformat等を選んで簡単に表示させることができるし、全般的な比較ならupdate reportを出してやれば現在の量が平年と比べて何%程度あるのか数値としてみることもできる。
具体的な使い方としてはtop pageからopen the mapへと進み、snow water equivalent, percent of official Medianへと進めばアメリカの地図上に観測所が点として表示され、それぞれの色で現時点で平年と比較してどのくらい(何%)積雪があるのか示される。さらに詳しいデータを見たい場合は見たい場所を拡大する。観測所の点の上にカーソルを持ってくるだけでその観測所の名前と標高、積雪は何%という数字がでるが、クリックしてやると実際の値や過去の最低最小値など詳細データがpopupして出て来る。このpopupの下の方にあるdata reportのwater year chartをクリックしてやると現在の積雪量とのべ降水量の平年と今年の比較がグラフで表示されこれまでの経緯と今後の予測が可能になる。各観測所のIDを覚えておけばtop pageからReport Generatorに直接進むことでこういったデータをいきなり作成することもできるようになるのでさらに興味がある方はいろいろと試してみてほしい。こんなのはめんどくさいとか大体わかればという向きには同じデーターを使っているのだがココがよいかも。昨年(2016年)は12月から1月前半に大雪が降って多い年なのかと心配したが、1月後半から2月にほとんど雪がふらなかった上、3月以降暖かい日が多く雪解けは例年よりも少し早めであった。今年(2017年)はWA, ORや北CAでは今のところ平年並みか若干多い程度だが、CA-NVは1月後半からはWinter stormが猛威を振るいここ3年の水・雪不足の反動なのか記録的な豪雪に見舞われているようだ。今年はSierra Nevadaの夏の訪れはいつもよりゆっくりかもしれない。