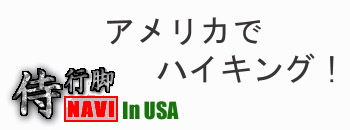Emergency kitとしては取り上げなかったが、Personal Locating Beaconという。救助信号を発信するシステムで遭難した時に使う発信機とGPSが合体したような装置がある。Hikeに限らず車に乗っていても遭難してしまうようなことがあるアメリカでは大変popularなもので遭難して助けが必要な時にスイッチを入れれば国際救難信号帯で救難電波を発信しはじめる。アメリカでは気象庁(NOAA)がこの電波を監視しており、救助要請が実施されるとともに内蔵GPSによって位置を割り出し救助隊が派遣されることになる。
電波は一日分程度しか持たないが、この方法で救助する場合、十分な長さのようだ。$200-400程度で小型の携帯程度の大きさなのでhikeに持っていくのも特に問題にはならないし、ホームセンターなどでもよく売られている。役に立つんだか立たないんだかよくわからない入山届けと家族・友人・会社からの通報によって起動する日本の遭難救助は救難が必要な状況に陥ってから2-3日経ってからようやく始まることが多く救助隊が組織された時には既に手遅れになっていることも少なくない。高齢者の登山・遭難の増加が大きな社会問題のひとつとなっている現状でこういったsolutionは救助される側からするとまるで救世主のように見えるのだが救助を実施する日本の関係機関にとってはそうでもないようだ。先にも書いたとおりこれは国際規格で国際的に使える。日本では毎度のことだが法整備が遅れていて、ようやく海難救助に限ってもうすぐ使用できるようになるらしい。あなたが海外に行ってPLBを購入し、日本国内で遭難した時にこれを使用した場合を考えてみよう。あなたがPLBを起動すると、PLBはただちに電波を発信し始める。この信号は地球上のどこで発射されても必ず衛星がキャッチし、各国政府が運用している受信局に連絡が届くことになっている。日本の場合、電波を監視しているのは海上保安庁で、海上保安庁にて救難信号が受信されることになる。得られた位置情報が日本の公海上であればこの信号は118番通報されたのと同じでこの信号により海上保安庁なり自衛隊なりに派遣が要請され救助活動がスタートすることになる。しかしながら発信位置が海でなく日本の陸上であった場合、遭難位置が特定できているにも関わらず、海上保安庁から山岳救助を担当する警察へ連絡をする仕組みが存在していないため、救難信号は無視され何も起こらず、残念ながらいくら待ってもあなたの知人等が通報しない限り、救援はこないことになる。確かに誤使用の問題がある(アメリカでは購入後使用するためにはNOAAのweb siteで登録する必要がある)が、国際規格なのに日本では使えないのは残念としかいいようがない。入山届を義務化するより、こういった仕組みづくり・法整備をすることにより国際的にも貢献できるだけでなく初動がはっきりとして救助の効率化および生存確率が格段に上がると思うのだが、そんな正論よりお役所同士の壁は高いらしい。というわけで日本のhikerにはほぼ役に立たないのだがアメリカやヨーロッパ等の先進各国では非常に有効なemergency solutionであるのでそこでhikeする機会には考えてみても良いと思う。
日本でも役に立つことを考えた場合もうすこしマシな手段としてSPOTという衛生通信ツールがある。これはGPSロガーに衛生テキスト通信機能がついたようなもので、携帯が通じないところでもテキストメッセージを送ることができる。やはり携帯電話程度の大きさと重さで所持することにたいして苦痛はない。ただしテキストメッセージといっても3種類の予め決められたメッセージを現在の位置情報と共に予め決めておいた連絡先にのみ送ることができるという機能なので詳細な状況を連絡できるわけではない。本体にはSOSボタンがついており、911等関係機関に連絡できるのだが、日本では衛星電話回線では110につながらない(!)ので機能しない。それでも連絡先の知人と予め取り決めしておけば位置情報を含めて警察に通報してもらうことは可能である。衛星電話契約をしているようなものなので本体購入金額以外に毎年$150程度の維持コストがかかるのが難点ではあるが、有効エリアは南極・北極などの両端とアフリカの一部を除けばほぼ全世界をカバーしており、まずどこでも使用できる。また単4電池で動作したりUSB充電が可能であったりするうえ、標準でGPSロガーとしては記録頻度にもよるが1週間ほどの連続使用は問題なく、スマホとは違い電池切れにも強そうなのも利点である。さらには位置情報を常に送る事ができるので遭難中に移動した場合でも容易にそれを伝えることが出来る。本体は定価$150だが、基本通信料で儲けるビジネスモデルに近いのでセール等が多く実質は半額以下で手に入ることができるようだ。他に良いsolutionがあっても自分のもっている手段にこだわり、自分に利ができるまでは利用者に情報提供もしないというのが日本のお役所の問題点のひとつなので、自分の身を守る手段としてこういうデバイスの情報などを集めることは真剣に考える価値があると思う。